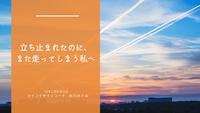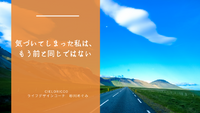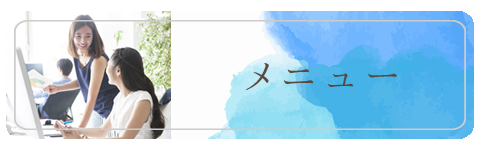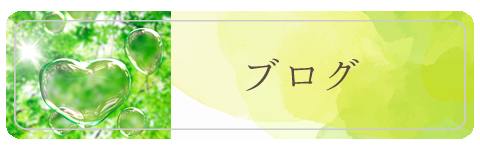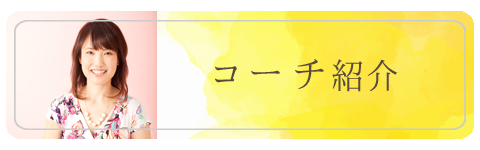信頼が芽生える関わりの力を、あなたの現場に。
ー未来を共に創る先生方へ
寄り添いながら、手放していく技術
伴走するとは、いつも隣で支えることではない。 信じて「手放す」という選択の先にある、育ちの瞬間。
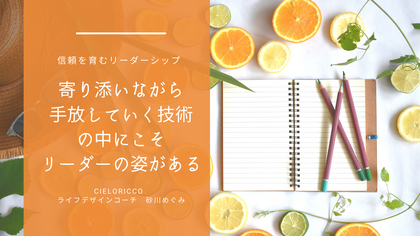
発表会での連弾は、生徒と私が一緒に舞台に立つ大切な機会です。
隣にいることで安心し、音を重ねることで心が通う。
でも、本当に大切なのは「ずっと隣にいること」ではありません。
「隣にいるけれど、本人の音を信じて任せること」。
連弾は、コーチングでいう“伴走”ととても似ています。
サポートしながらも、手を出しすぎない。
信じて待つことで、自分で奏でる力が育っていくのです。

つい口を出したくなる瞬間、音を合わせたくなる場面、
たくさんあります。
でもそのたびに、私は少しずつ“手放す”練習をしています。
寄り添いながら、信じて任せる。
それは、音楽も人生も共通の “育ちの技術” なのだと思います。
この「寄り添いながら、手放す」という在り方は、
教育の場面だけでなく、管理職や組織のリーダーにとっても非常に重要なリーダーシップのスタンスです。
マネージャーや管理職という立場に立つと、「指導」「管理」「判断」といった言葉が先行しがちです。
部下の成果に責任を持つ立場として、
何かがうまくいかない時には、つい介入したくなります。
アドバイスをしたり、先回りしてフォローしたり、
場合によっては「私がやった方が早い」と自ら対応してしまうこともあるでしょう。
ですが、信頼されるリーダーとは、
常に前に出る人ではなく、必要な時には一歩引いて、部下が自分で考え、挑戦し、失敗し、成長するプロセスを信じて見守る人です。
私がコーチとして接する多くのリーダーたちとの対話の中で、
よく挙がるテーマのひとつが「どこまで任せていいのか」という葛藤です。
特に多く聞かれるのは「最終判断を手放すのが怖い」という声です。
どこかで「自分の方が経験があるから」「最終的には自分が責任を取らなければならないから」と、
無意識に主導権を握ってしまっているケースが多いように感じます。
任せること、そして手放すことには、不安が伴います。
結果が出なかったらどうしよう。
失敗してしまったらどうしよう。
けれど、その不安に寄り添いながらも、
「自分で考えて動いてもらう」経験を部下にさせなければ、組織としての成長は起きません。
寄り添うとは、相手のペースや状態に応じて、そばにいること。
この2つが両立して初めて、“育む”リーダーシップが生まれます。

ピアノの連弾で、私は「音を合わせにいかない」練習をしています。
先に弾いてしまうことで、生徒が“合わせてもらえる”ことに慣れてしまうと、自分から音を聴く力が育ちにくくなるからです。
管理職のリーダーシップも同じです。
リーダーがすべての調整役になってしまうと、部下が“考えて動く力”を身につける機会を奪ってしまいます。
信頼されるリーダーとは、「あの人が一緒にいるから安心」だけでなく、
「あの人が任せてくれるから、私は本気になる」と思わせてくれる人です。
安心感と挑戦心。
この2つを同時に育てる関わり方こそが、寄り添いながら手放す技術です。
コーチングにおいても、相手が自分で気づき、行動するために
「問いを届ける」「静かに待つ」「信じて任せる」ことが基本としています。
指導者、管理職、保護者、すべての“育てる役割”において必要なのは、手出しよりも“手を添える”。先導よりも“横にいる”。
そうして相手が自らの足で歩み始めた時に、「本物の成長」が始まるのだと、私は信じています。
育ちを信じ、そっと支えながら、必要な時には一歩下がる。
そんなリーダーの背中を、子どもも、大人も、しっかりと見ているのだと思うのです。
-
 わかっているのに、元の私に戻ってしまう日
それでも日常は続いていく 自分の中にあった違和感や、言葉にならなかった気持ちに気づいたあとも、私たちは、変わら
わかっているのに、元の私に戻ってしまう日
それでも日常は続いていく 自分の中にあった違和感や、言葉にならなかった気持ちに気づいたあとも、私たちは、変わら
-
 立ち止まれたのに、また走ってしまう私へ
立ち止まれたと思ったのに、気づいたら、また前と同じ速さで動いている。そんな自分に、がっかりしたことはありません
立ち止まれたのに、また走ってしまう私へ
立ち止まれたと思ったのに、気づいたら、また前と同じ速さで動いている。そんな自分に、がっかりしたことはありません
-
 それでも、何かが前と違っている
何も変えていないはずなのに、同じ一日を過ごしているはずなのに、「前と同じじゃないかもしれない」そんな感覚が、ふ
それでも、何かが前と違っている
何も変えていないはずなのに、同じ一日を過ごしているはずなのに、「前と同じじゃないかもしれない」そんな感覚が、ふ
-
 気づいてしまった私は、もう前と同じではない
元に戻ったような日もある。進んだ実感がない日もある。それでも、もう前と同じではないと、どこかでわかっている。そ
気づいてしまった私は、もう前と同じではない
元に戻ったような日もある。進んだ実感がない日もある。それでも、もう前と同じではないと、どこかでわかっている。そ
-
 気づいた翌朝も、日常は変わらず始まる
見えなかった自分の前提が、見えてしまった。自分の感情や反応、疲れを、無視できなくなった。だから「前と同じ自分」
気づいた翌朝も、日常は変わらず始まる
見えなかった自分の前提が、見えてしまった。自分の感情や反応、疲れを、無視できなくなった。だから「前と同じ自分」
未来デザインコーチング チェーロリッコ
先生・講師のための、信頼を育むリーダーシップ
メールアドレス : info@cieloricco.com
電話番号:0745-43-6158
個人セッション可能時間:9:00〜15:00 (月〜土)その他、応相談
定休日 : 日祝
所在地 : 奈良県大和高田市日之出西本町4-1末広堂ビル3F サロン情報はこちら